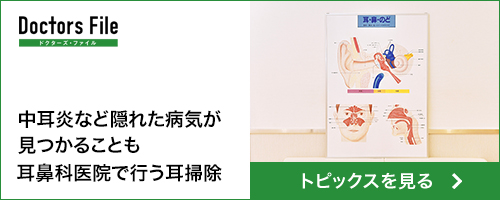脳神経内科
脳神経内科とは

脳神経内科は、脳をはじめ、脊髄、神経、筋肉の病気を専門に診る診療科です。
頭痛やめまい、手足のしびれ、震えといった症状をはじめ、脳梗塞やパーキンソン病などの病気の原因が脳神経系のどこにあるのかを診断します。
診断に基づいた適切な治療を提供するほか、原因によっては、整形外科や眼科、精神科など、より専門的な医療機関をご紹介いたします。
また、アルツハイマーなどの認知症の診断・治療も神経内科の領域です。認知症については、認知機能テストを行い、その判定結果から診断します。
主な症状
- めまい
- 頭痛
- 手足のしびれ
- 手足の震え
- もの忘れ
- ひきつけ
- 脱力
- ものが二重に見える(複視)
主な病気
- 認知症
- 脳梗塞
- てんかん
- パーキンソン病
- 神経難病
生活習慣病(糖尿病、高血圧、高脂血症等)
生活習慣病

人間は年齢を重ねると新陳代謝のスピードが衰え、体力も低下していきます。
しかし逆に、仕事をしている方は年齢を重ねるほど社会的な地位が上がって忙しくなります。家庭においても家事育児などの負担が増え、ご自分の食事や睡眠がおろそかになりがちです。
日々やるべきことの量が増えるとストレスも増えます。ストレスは暴飲暴食や睡眠不足、運動不足を招き、生活のリズムを乱します。こうした不健康な生活の積み重ねが、やがて体を蝕んでいきます。それが、生活習慣病です。
生活習慣病の主なものとして、以下の4つが挙げられます。
- 糖尿病
- 高血圧
- 脂質異常症
- 肥満
これらはすべて毎日の生活習慣が原因で引き起こされるため、複数の病気を併せ持っている方も少なくありません。
生活習慣病を放置しておくと、気づかぬうちに進行し、脳卒中や心臓発作などの命にかかわる病気がある日突然、起こることがあります。生活習慣病は重症化する前に発見し、適切な治療を行いながら生活習慣を正すよう努めることが何より重要です。
糖尿病について
糖尿病とはどのような病気か
糖尿病とは、血糖値(血液中のブトウ糖濃度)が病的に高い状態を指す病気です。糖尿病の深刻な合併症(神経障害、網膜症、腎症、動脈硬化症など)を引き起こすことがあり、最悪の場合は、死に至る危険な病気です。早めの治療・対策が必要です。
治療には運動療法、食事療法、内服薬による薬物療法を行います。
1型と2型の違いについて
糖尿病には1型と2型があります。
1型は、インスリンをつくる膵臓の細胞が壊れ、本来生まれ持って備わっている血糖値を下げる機能が働かなくなることが原因で起こる糖尿病です。
一方、遺伝的要因に加え、過食や多飲・運動不足などの環境要因が重なって発症するのが2型糖尿病です。日本で一般的に「糖尿病」という場合は、ほとんどが2型糖尿病を指し、実際、患者数も多い病気です。
糖尿病になりやすい人
糖尿病は肥満や運動不足が原因で起こるため、糖質の摂りすぎなど食生活に偏りがある方や肥満傾向の方、定期的に運動する習慣がない方は要注意です。遺伝的要素に加えて毎日同じ食事を口にすることから、家族に糖尿病の方がいる方もリスクは高いといえます。
私生活で注意すること
- 食べすぎない(エネルギーを摂りすぎない)
- 定期的に運動をする
- お酒を飲みすぎない
- タバコを吸わない
- 規則正しい生活を送る
- 野菜や大豆製品、海藻、きのこなどを多く食べる

高血圧について
高血圧とはどのような病気か
日本国内の高血圧患者は、約4,300万人と推定されます。高血圧を放置すると、動脈硬化が進行し脳卒中(脳梗塞、脳出血)や心筋梗塞あるいは腎臓病のリスクが高まります。
治療は血圧が140/90mmHgを超えたからといってすぐに薬を飲むのでなく、まずは生活習慣の改善(食事内容を見直し塩分摂取量を減らす・減量する・運動するなど)から始めてください。
生活習慣の改善を試みても効果が認められなければ、内服薬の適応となります。高血圧の薬はたくさんありますが、ご自身に合ったものを内服することが重要です。
高血圧になりやすい人
高血圧は肥満と深い関わりがあり、肥満の方が多い睡眠時無呼吸症候群の患者さまの中にも高血圧の方が多い傾向にあります。また、同じ生活習慣病である糖尿病の方やその傾向がある方にも、血圧が高い人が多くいます。
また、よくいわれる塩分の摂りすぎだけでなく、食べすぎや消化不良、栄養素の過不足も高血圧の原因となります。
運動は血流を促すため、運動習慣がない方も高血圧になりやすいといえます。
私生活で注意すること
- 食事の塩分を控える
- 肥満を改善するよう努める
- 定期的に運動をする
- タバコを吸わない
- 節酒を心がける
高脂血症
高脂血症について
高脂血症とは、血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂質が、一定の基準よりも多い状態のことをいいます。
血液中に余分な脂質が多くなると、動脈硬化を起こしやすくなり、脳卒中や心筋梗塞などのリスクが高くなります。糖尿病、高血圧と同様に自覚症状に乏しいため、放置してしまいがちで注意が必要です。
健康診断や人間ドックで高脂血症を指摘されたら、一度当院へお越しください。
治療は、まず生活習慣の改善から始めます。2~3ヶ月してもコレステロール値が改善しない場合に内服薬による治療を検討します。
高脂血症になりやすい人
高脂血症は、食生活の偏りと運動不足が大きな原因となっています。
コレステロールを多く含む食品のほか、血中コレステロールを上げる飽和脂肪酸を多く含む動物性脂肪や、工業的に作られたトランス脂肪酸は、高脂血症のリスクを高めます。
また、このような食生活のほか、運動不足で肥満になっている人も高脂血症を起こしやすい傾向にあります。
肥満について
肥満とは

肥満は、体重が過剰な状態です。体格指数(BMI)を使用して評価します。
肥満の判定基準は、BMIが25以上になると肥満、BMIが35を超えると高度肥満になります。
肥満症の治療は、日々の体重や食事内容を記録する「行動療法」、摂取エネルギーを押さえるための「食事療法」、週3日以上、20分以上の運動を実施することによる糖尿病や高血圧・高脂血症の改善などの「運動療法」を合わせて減量治療を行います。
肥満になりやすい人
カロリーの過剰摂取となる食べ過ぎはもちろんのこと、肥満には、食事の回数や食事を摂る時間帯も大きく関わっています。
朝食と昼食を食べずに夜だけたくさん食べたり、眠る前の深夜に食事をしたりすることなども肥満の原因となります。
また、肥満は遺伝も関係するといわれますが、遺伝的要因よりも、毎日同じ食事を摂取している環境的な要因が大きいといえます。